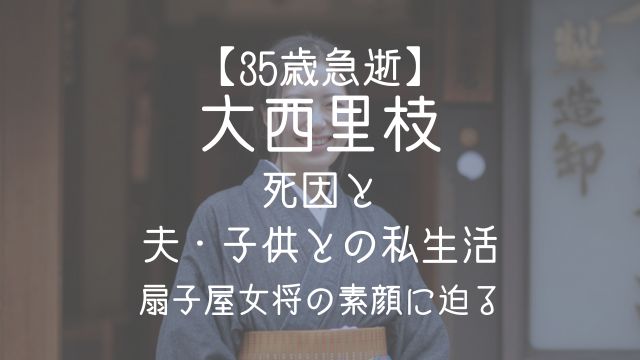*アフィリエイト広告を利用しています。
2025年8月22日、京都の老舗扇子店「大西常商店」の4代目社長であり、“扇子屋女将”として親しまれていた大西里枝さんが、35歳という若さで急逝されました。
SNSやメディアを通じて、伝統文化を発信し続けた彼女の突然の訃報は、多くの人々に衝撃を与えています。
そこで今回の記事では、
・夫、子供
・扇子屋女将として功績
・大西里枝さんの素顔と人柄
の4つのポイントに沿って、大西里枝さん死因の情報、夫・子供との私生活、そして彼女の素顔や経歴に迫りながら、なぜこれほど多くの人に愛されたのかを紐解いていきます。
大西里枝さん急逝の報道と死因の非公表

2025年8月22日、京都の老舗扇子店「大西常商店」の4代目社長であり、“いけず女将”としても知られていた大西里枝さんが、自宅で急逝されたという報道がありました。
35歳という若さでの突然の訃報は、SNSや報道を通じて瞬く間に広まり、多くの人々に衝撃を与えました。
死因は現在も公表されておらず、SNSアカウントの削除なども重なり、ネット上ではさまざまな憶測が飛び交っています。
このセクションでは、報道のタイミングと内容、死因非公表の背景、そして家族の対応から見える配慮について、事実に基づいて整理します。
訃報の概要と報道タイミング
大西里枝さんの訃報は、2025年8月22日に京都新聞など複数の報道機関によって伝えられました。
亡くなった場所は京都市下京区の自宅とされており、享年は35歳です。
報道では「急逝」とのみ記され、死因に関する詳細は明かされていませんでした。
SNSでは、彼女が8月5日にX(旧Twitter)で、秋の台湾旅行やイベント出演の予定を投稿していたことが確認されており、直前まで通常通りの活動をしていた様子が見受けられます。
このような状況から、突然の訃報に驚きと戸惑いの声が広がりました。
《広告の下にコンテンツが続きます》
死因が非公表である理由と憶測の広がり
現時点で、大西里枝さんの死因は正式に公表されていません。
報道各社も「急逝」とのみ伝えており、家族からのコメントも出されていない状況です。
このため、ネット上では「心臓や脳の疾患による急性の病気ではないか」「家庭内での事故の可能性もあるのでは」といった推測が一部で見られています。
ただし、これらはあくまで状況に基づく一般的な憶測であり、医学的・報道的な根拠は示されていません。
本人が健康上の問題を公にしていなかったことや、予定が立て込んでいたことも、憶測を呼ぶ要因となっています。
こうした「情報の空白」があることで、関心が高まる一方、誤解や混乱も生じやすくなっているのが現状です。
《広告の下にコンテンツが続きます》
SNS削除と家族の対応から読み取れる配慮
訃報が報じられた直後、大西里枝さんのX(旧Twitter)やFacebookなどのSNSアカウントが削除されたことが確認されています。
彼女のSNSは、京都文化や日常の出来事をユーモアを交えて発信する場として、多くのファンに親しまれていました。
そのため、突然の削除に驚きの声が上がり、「死因非公表」との関連を疑う声も一部で見られました。
しかし、現時点でSNS削除と死因の間に直接的な関係を示す情報は出ていません。
むしろ、家族や関係者がプライバシー保護や混乱回避のために、アカウントを整理した可能性が高いと考えられます。
SNSは、発信者が不在となった後に誤解や憶測を招くことがあるため、削除という選択は“防衛的配慮”とも受け取れます。
特に、9歳の息子がいる家庭であることを踏まえると、遺族が静かな環境を守るために慎重な対応を取ったと見ることができます。
《広告の下にコンテンツが続きます》
夫・子供との私生活と家族構成

出典元:dot.asahi
公私ともに充実した日々を送っていた大西里枝さんは、夫・大西裕太さんと9歳の息子との3人暮らしでした。
NTT西日本での勤務経験を共有する夫との協力関係は、家業の継承にも大きな力となっていました。
家庭では役割分担を明確にしながら、日々の生活を丁寧に築いていた様子が報道やインタビューからうかがえます。
このセクションでは、夫婦の馴れ初めから育児スタイル、そして家族で取り組んだ伝統産業の革新についてご紹介します。
夫・大西裕太さんとの馴れ初めと結婚生活

大西里枝さんと夫・裕太さんは、NTT西日本の同僚として出会いました。
里枝さんが熊本、裕太さんが福岡に勤務していた時期に、共通の知人を通じて知り合ったそうです。
交際に発展したのは出会いからわずか1〜2か月後で、9か月後には結婚に至るというスピード婚でした。
結婚後は裕太さんが婿入りし、大西常商店の業務にも協力するようになります。
家庭では、料理を里枝さんが担当し、それ以外の掃除・洗濯・育児などは裕太さんが担っていたと報じられています。
また、月に一度は夫婦で20kmのマラソンに挑戦する習慣があり、健康管理にも積極的でした。
SNS投稿や商品開発の相談も夫婦間で行われており、互いに支え合う姿勢が日常に根付いていたことが分かります。
《広告の下にコンテンツが続きます》
息子との日常と育児スタイル

大西里枝さんには、2025年時点で9歳になる息子がいます。
出産をきっかけに家業を継ぐ決意が固まったと語っており、息子の存在が人生の転機となったことがうかがえます。
家庭では、毎朝3人で朝食を囲む習慣があり、家族の時間を大切にしていたと報じられています。
育児は夫婦で分担しており、SNSでは「長男と裕太さんが一緒に洗濯物をたたむ」様子が投稿されていたこともあります。
息子の名前や顔写真は公開されておらず、プライバシーへの配慮が徹底されていました。こうした姿勢からも、家族を守る意識の高さが感じられます。
家族で築いた伝統産業の新しい形

大西里枝さんは、NTT西日本での経験を活かし、家業の「大西常商店」にIT化や商品開発の視点を持ち込みました。
夫・裕太さんも業務に関わり、在庫管理アプリの導入やクラウドファンディングによる、町家改装プロジェクトなどを支えました。
特に、扇子の骨を使ったルームフレグランス「かざ」や、観光客向けの体験型スペースの創出は、家族の協力があってこそ実現した取り組みです。
伝統を守るだけでなく、現代のニーズに応える革新を家族で推進していた姿勢は、多くのメディアでも高く評価されています。
《広告の下にコンテンツが続きます》
扇子屋女将としての挑戦と功績

大西里枝さんは、NTT西日本での企業経験を経て、京都の老舗扇子店「大西常商店」の4代目社長として家業を継承しました。
伝統を守るだけでなく、現代の感性を取り入れた商品開発や文化発信に積極的に取り組み、地域と観光の架け橋となるような事業展開を行ってきました。
このセクションでは、彼女がどのような経緯で家業に携わるようになったのか、具体的な商品やプロジェクト、そして「いけず文化」を活用した観光資源化の取り組みについて紹介します。
NTT退職から家業継承までの経緯
大西里枝さんは、2012年に立命館大学政策科学部を卒業後、NTT西日本に入社しました。
福岡・熊本・京都の各地で光回線サービスの営業職として勤務し、4年間の企業経験を積みました。
2016年、出産を機に退職し、京都市下京区にある実家の扇子店「大西常商店」に若女将として入社します。
家業では、接客・卸・商品企画・広報など幅広い業務を担当し、伝統産業の現場を実務から学びました。
2023年7月には父から社長職を引き継ぎ、4代目として正式に就任。
社長就任後は、デジタル化や新規事業の立ち上げに注力し、扇子業界に新しい風を吹き込む存在となりました。
《広告の下にコンテンツが続きます》
伝統×現代の融合商品とクラウドファンディング

社長就任後、大西里枝さんは扇子の素材を活用した新商品「かざ(KAZA)」を開発しました。
これは、扇子の骨を使ったルームフレグランスで、香りと伝統工芸を融合させた画期的な商品です。
従来の扇子の用途を超えた提案として、若年層や海外観光客からも注目を集めました。
また、町家の改装資金を集めるためにクラウドファンディングを活用し、観光客向けの体験型スペースを創出しました。
このプロジェクトでは、扇子づくりの工程を実際に体験できる場を提供し、伝統文化への理解を深める機会を提供しています。
資金調達と地域活性を両立させた取り組みとして、メディアでも高く評価されました。
《広告の下にコンテンツが続きます》
「いけず文化」発信と観光資源化の取り組み
大西里枝さんは、京都特有の“いけず文化”をユーモラスに解釈し、観光資源として発信する活動にも力を入れていました。
代表的な取り組みが「いけずステッカー」の企画です。

これは、京都人の建前と本音を表裏で表現したステッカーで、「表:お暑いですね」「裏:そんな格好してるからやろ」といった言葉遊びが特徴です。
このステッカーは、観光客に京都文化の奥深さとユーモアを伝えるツールとして人気を集め、SNSでも話題になりました。
単なるジョークではなく、京都人の気遣いや美意識を伝える文化的コンテンツとして、地域の魅力を再発見するきっかけとなっています。
こうした発信は、伝統産業の枠を超えた文化プロデュースの一環として位置づけられています。
《広告の下にコンテンツが続きます》
大西里枝さんの素顔と人柄

伝統産業の担い手としてだけでなく、日常の振る舞いや発信スタイルからも、大西里枝さんの人柄は多くの人に親しまれていました。
和服を普段着として着こなし、SNSではユーモアと知性を交えた発信を続けるなど、彼女の生活には京都文化への深い愛情と柔軟な感性が息づいていました。
このセクションでは、彼女のこだわりや価値観が垣間見える具体的なエピソードを通して、その素顔に迫ります。
和服生活と文化へのこだわり

大西里枝さんは、家業に戻った2016年以降、洋服をほとんど処分し、日常的に和服を着用する生活を続けていました。
最初は仕事着として着物を選んでいましたが、「普段から着ていないと洋服に逃げてしまう」との理由で、完全に和服中心の生活に切り替えたと語っています。
着物の収納力を活かした生活スタイルも話題になりました。
帯にはスマートフォン、懐には領収書や名刺、袖にはゴミまで入れていたとSNSで紹介し、「着物はバッグ代わりになる」との投稿には、約9万件の「いいね」が寄せられました。
特に、魚型の醤油入れを袖に入れたまま洗濯してしまい、夫に叱られたというエピソードは、彼女のざっくばらんな人柄を象徴するものです。
《広告の下にコンテンツが続きます》
SNSで見せたユーモアと知性
SNSでは「扇子屋女将」として、京都文化や日常の出来事をユーモアを交えて発信していました。
代表的な企画が「いけずステッカー」で、京都人の建前と本音を表裏で表現したデザインが話題を呼びました。
「表:お暑いですね」「裏:そんな格好してるからやろ」といった言葉遊びが観光客に人気を集め、京都文化の奥深さを伝えるツールとして注目されました。
また、着物の便利さや収納力についての投稿では、実体験に基づいたユニークな視点が多くの共感を呼びました。
帯にスマホを挿して紛失防止に役立てたり、袖にエコバッグ代わりに物を入れて持ち帰るなど、実用性と文化的魅力を融合させた発信が特徴的でした。
地域・家族・仕事に向き合う姿勢

大西里枝さんは、地域文化の担い手としての責任を強く意識していました。
京町家を活用した文化体験事業では、投扇興や茶席体験、絵付け体験などを通じて、観光客に京都の伝統を身近に感じてもらう工夫を重ねていました。
家庭では、夫と息子との時間を大切にし、毎朝3人で朝食を囲む習慣を続けていたと報じられています。
育児や家事は夫婦で分担し、SNSでも「長男と夫が洗濯物をたたむ様子」が投稿されていたことがあります。
仕事では、NTT西日本で培った提案力を活かし、家業のIT化や商品開発に取り組むなど、実務面でも着実な成果を残しました。
このように、地域・家族・仕事のすべてに誠実に向き合いながら、文化と人とのつながりを大切にする姿勢が、多くの人に信頼と共感を与えていたのです。
《広告の下にコンテンツが続きます》
まとめ|なぜ彼女は多くの人に愛されたのか

大西里枝さんの訃報は、伝統産業の担い手としてだけでなく、地域文化の発信者、家庭人としての姿にも注目が集まりました。
彼女が築いてきたのは、単なる事業の成功ではなく、人と文化をつなぐ温かな関係性です。
このセクションでは、文化的な影響力、家族との絆、そして今後予定されている「お別れの会」など、彼女が人々に愛された理由を振り返ります。
文化の担い手としての存在感
大西里枝さんは、京扇子という季節性の高い伝統商品に危機感を持ち、扇子の骨を使ったルームフレグランス「かざ」や、京町家を活用した文化体験スペースの創出など、革新的な取り組みを続けてきました。
2022年には、ツギノジダイのオンラインイベントに登壇し、星野リゾートの星野佳路氏から「京都で110年続いているということは、世界的な視点で見ると価値がある」との助言を受けたことも報じられています。
また、「いけずステッカー」を通じて、京都人の本音と建前をユーモラスに伝えるなど、文化の“翻訳者”としての役割も果たしていました。
SNSでは「菖蒲打ち」などの伝統行事を紹介し、地域の魅力を親しみやすく発信する姿勢が、多くの人に共感を呼びました。
《広告の下にコンテンツが続きます》
家族とともに生きた人生の深み

夫・裕太さんとの結婚は、出会いから9か月でのスピード婚でしたが、家業への婿入りや業務協力など、強い信頼関係に支えられていました。
家事や育児は分担し、毎朝3人で朝食を囲む習慣を続けていたことが報道されています。
SNSでは、長男と夫が洗濯物をたたむ様子を投稿するなど、家庭の温かさが垣間見える場面もありました。
出産を機にNTT西日本を退職し、家業に戻ったという経緯からも、家族の存在が人生の選択に大きな影響を与えていたことが分かります。
伝統産業の継承と育児を両立させながら、地域と家庭の両方に誠実に向き合う姿勢は、多くの人に尊敬されていました。
今後の「お別れの会」や追悼の動き
大西里枝さんの死去は、2025年8月22日に大西常商店のSNSを通じて公表されました。
葬儀は家族の意向により近親者のみで執り行われ、供花・供物・香典は辞退されています。
その一方で、後日「お別れの会」を開く予定であることが明らかにされており、関係者やファンが彼女を偲ぶ場が設けられる見込みです。
喪主は夫・裕太さんであることが報じられており、家族が静かに見送る形を選んだことからも、プライバシーと配慮を重視した姿勢が感じられます。
今後の会では、彼女の功績や人柄に触れる展示や、メッセージの共有などが行われる可能性があり、文化的な影響力を再確認する場となるでしょう。
いかがでしたでしょうか?
大西里枝さんが遺した温もりと挑戦の軌跡は、これからも京都の風に乗って語り継がれていくでしょう。
静かにその存在を偲びながら、私たちは彼女の生き方から多くを学び続けています。