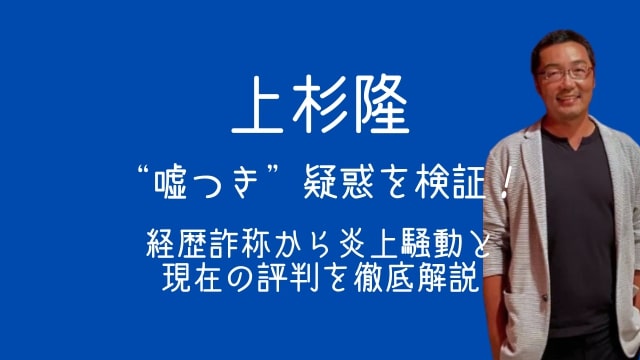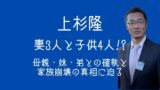*アフィリエイト広告を利用しています。
「噓つき」と呼ばれるジャーナリストの上杉隆さん。
上杉隆さんは、一体なぜそんなレッテルを貼られるようになったのでしょうか?
そこで今回の記事では、
・上杉隆の炎上騒動の経緯
・上杉隆と立花孝志の裁判
・上杉隆の現在の評判
の4つのポイントに沿って、上杉隆さんにまつわる”噓つき疑惑”の全容を検証し、現在の評判についても分析してみたいと思います。
上杉隆が”噓つき”と呼ばれる理由とは?

「報道の自由」を掲げながらも、たびたび”噓つき”と批判される上杉隆さん。
その背景には、報道内容の事実誤認、肩書の曖昧さ、そして、著作権に関する訴訟などが絡んでいます。
ここでは、信頼性への疑問が持ち上がるきっかけとなった具体的な事例を元に、「なぜ噓つきとよばれるのか」を検証します。
報道内容の誤りと訂正履歴
上杉隆さんは、福島第一原発事故の取材時に、「いわき漁港」という架空の地名を使用したことが指摘され、報道の正確性に疑問が呈されました。
さらに、ウォール・ストリート・ジャーナル(WSJ)の記者の発言を引用した記事に関して、WSJ側が「その発言は存在していない」と、訂正を求める事態に発展したこともありました。
これらの修正事例は、「取材不足による誤報」と捉えられ、信頼性を損なう原因となっています。
《広告の下にコンテンツが続きます》
経歴詐称疑惑と肩書の不一致
「ジャーナリスト」「政治評論家」としてメディア出演してきた上杉隆さんですが、一部では「本当に報道機関に所属していたのか?」「肩書きの根拠は何か」と疑問視される声があります。
特に、元「ニューヨーク・タイムズ東京支局記者」を名乗っていたことに対して、「記者として正式に採用された形跡がない」と指摘されたことで、肩書きへの不信感が広がりました。
こうした経歴の食い違いが、”噓つき”というレッテルに繋がったと考えられます。
著作権侵害訴訟と裁判記録
2005年には、読売新聞の記事を自身のブログに無断転載したことで著作権侵害が認定され、東京高裁で敗訴しています。
判決では「報道の範囲を超えて営利目的で利用された」と判断され、法的な信用も損なう結果となりました。
この件は、報道姿勢そのものに対する疑念を生む要因となり、情報発信者としての信頼性に影響を与えています。
《広告の下にコンテンツが続きます》
上杉隆の炎上騒動の経緯と世間の反応

「噓つき」というイメージは、報道内容だけではなく、テレビ番組やSNS上での扱われ方によっても加速することがあります。
上杉隆さんも例外ではなく、ネット上でネガティブなキーワードの連携や、メディアでの露出のされ方が炎上に繋がった一因となっています。
ここでは、炎上が広がったメディア的背景と、世間の反応、そして、それに対する本人の抗議や声明を整理します。
SNSやテレビ番組での扱い
TBSの番組『サンデー・ジャポン』では、検索トレンドを紹介するコーナーで「噓つき」「炎上」というワードをもとに、上杉隆さんの名前が取り上げられました。
この演出がSNS上で拡散され、彼にイメージを大きく左右する一因になりました。
特定の意図を感じさせる紹介の仕方により、「虚偽報道の象徴」としてネットユーザーの間で定着し始めました。
また、X(旧Twitter)やYouTubeでも、「上杉隆 炎上」「上杉隆 噓つき」などのハッシュタグや動画タイトルが頻繁に登場し、情報が断片的に拡散される中で、誤認や印象操作も助長されたと見られます。
《広告の下にコンテンツが続きます》
「噓つき」イメージ形成のきっかけ
上杉隆さんのイメージが定着するきっかけとして大きかったのは、いくつかの報道訂正事件に加えて、メディアにおける”見せ方”です。
肩書きや発言が一部で誇張されたり、前述の「いわき漁港」問題などが”虚偽報道”の代表例として紹介されたことで、「上杉隆=信頼できない人物」という認識が一定層に広まりました。
さらに「記者クラブ制度への批判」など、上杉隆さんのスタンス自体が既存メディアと対立するものであったことも、反発を受けやすい構造を生んでいたと考えられます。
本人による反論と抗議の内容
こうした炎上に対して、上杉隆さんはSNSや動画配信を通じて、たびたび反論を行っています。
特に、「虚偽報道」「噓つき」と呼ばれることについては、「事実に基づいた取材である」「既得権益層の攻撃だ」と強く否定し、法的措置を取る姿勢も見せました。
TBS番組の件に関しては、本人が「名誉棄損にあたる」として抗議文を提出したと報じられています。
番組側がどこまで対応したかは不明ですが、「メディアへの圧力」と受け止める声もあれば、「正当な抗議」と見る支持者の意見も存在しています。
《広告の下にコンテンツが続きます》
上杉隆と立花孝志の訴訟履歴まとめ

炎上騒動が世間的な印象を左右する一方で、訴訟記録はより客観的な評価に繋がります。
上杉隆さんと立花孝志さんの間では、複数の名誉棄損や損害賠償をめぐる法的対立が繰り返されてきました。
ここでは、それぞれの裁判内容と結果を整理しつつ、判例を通じて”信頼性”がどのように揺らいだのかを分析します。
名誉棄損裁判と賠償命令の判決
2024年8月、東京地裁にて上杉隆さんが名誉棄損で敗訴し、立花孝志さんに対して30万円の賠償支払いを命じられました。
発端は、上杉隆さんが「立花孝志氏に対する選挙妨害や公選法違反の捜査が継続している」と発言したことにあり、立花孝志さん側は「事実無根」として提訴しました。
裁判所は「発言に対する十分な根拠が示されなかった」と判断し、名誉棄損が成立すると結論付けました。
この判決は、言論の自由と発信の責任を分けて考える上で、重要な示例となっています。
《広告の下にコンテンツが続きます》
嵐の党(旧NHK党)との損害賠償訴訟
2021年には、嵐の党(当時のNHK党)が上杉隆さんに対して、264万円の損害賠償請求を行いました。
理由は、週刊誌報道に関する釈明会見に、上杉隆さんが出席しなかったことが「党の信用を損ねた」というものでした。
この裁判は東京地裁で審理されましたが、上杉隆さんの反論により棄却されています。
さらに別件の訴訟では、裁判官が「党の主張は感情的すぎる」と口頭で評したとも報じられており、原告側の信頼性にも疑問が投げかけられる結果となりました。
判例から見える信頼性への影響
複数の訴訟を通じて浮かび上がるのは、上杉隆さんが「噓つき」と批判される背景に、法的判断が一部根拠になっているという点です。
名誉棄損での敗訴は確かに信頼を揺るがす要素ですが、逆に他の裁判では勝訴しており、一方的な評価では測れない側面もあります。
これらの判例は、政治的な発言や報道活動に対してどこまで責任を負うべきか、また、信頼性は何によって構成されるかを考える材料になります。
信頼は司法によって「証明される」場合もあれば、「揺らぐ」場合もあるということです。
《広告の下にコンテンツが続きます》
上杉隆の現在の評判

一連の騒動と炎上を経て、現在の上杉隆さんはどのような立ち位置にあるのでしょうか。
報道活動は継続しているのか、メディアでの扱いに変化はあったのか、そして、ネット上での評判は好転したのか。
ここでは、報道現場での動向からファン・批判層の声、そして「噓つき」疑惑が今も影響しているのかを分析し、現在の実像に迫ります。
報道活動やメディア露出の変化
上杉隆さんは近年、メディア出演は減少傾向にあり、大手報道番組での露出はほとんど見られなくなっています。
一方、YouTubeやXなど、自身の発信媒体を軸に活動を継続しており、インターネット上での報道スタイルへとシフトしている印象があります。
また、ジャーナリズムに関する講演活動や執筆は継続されているものの、かつてのように主流メディアの中枢に関わる機会は減り、言論空間の”周縁”で活動を続けている状態と言えそうです。
《広告の下にコンテンツが続きます》
ネット上の評価とファン・批判層の意見
インターネット上では今でも賛否が分かれており、支持者は「記者クラブ制度に切り込んだジャーナリスト」として評価し続ける一方、批判的な層は「虚偽報道を繰り返した人物」として警戒しています。
XやYouTubeのコメント欄では、「上杉隆さんの勇気は本物」「彼だけが本当のことを言っている」といった支持の声が見られる一方で、「事実と向き合わない姿勢が不快」「また嘘を言っているのでは」という懐疑的な声も存在しています。
特に、訴訟敗訴後のタイミングでは、炎上的な投稿が増える傾向があり、評価の揺れが続いている状況です。
”噓つき”疑惑が今も影響しているのか?
結論から言えば、”噓つき”というイメージは今も一定の影響力を持っているようです。
Google検索でも関連キーワードとして、「上杉隆 噓つき」「虚偽報道」などが表示されており、過去の炎上・訴訟の履歴が検索エンジン上で残り続けていることが、イメージの再構築を難しくしています。
一方で、強い支持を集めている層にとっては、過去の疑惑よりも”言論活動の姿勢”に価値を見出しているため、完全に評価が失われているわけではありません。
つまり、”信頼性の回復”は一部に可能性を残しつつも、”疑念の残存”という形で現在も影響しているということのようです。
いかがでしたでしょうか?
今後も益々話題となりそうな上杉隆さんを、引き続き注目していきたいと思います。